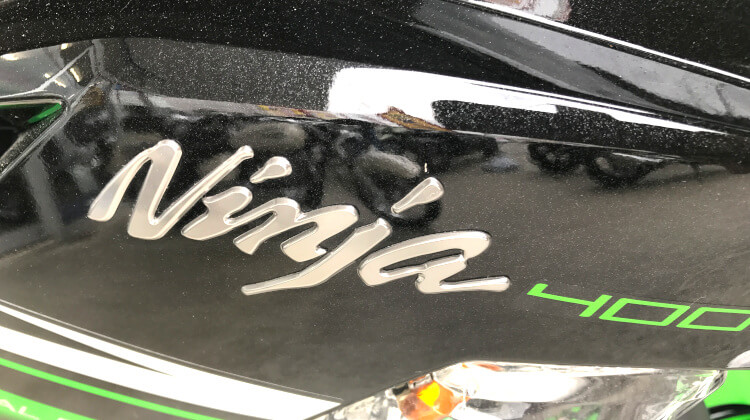インカムを利用するメリット
インカムは単なる連絡手段ではなく、ツーリングの安全性と楽しさを飛躍的に向上させるツーリングのマストアイテムです。
安全性と快適性の向上
最大のメリットは、安全性の向上です。
走行中に危険を察知した際や、急なルート変更が必要になった場合に、すぐに仲間へ情報を共有できます。
これにより、スムーズで安全な集団走行が可能になります。
また、ナビアプリの音声案内や、スマートフォンの音楽を走行中にクリアな音質で楽しめるため、ツーリング中の快適性も大きく向上します。
ツーリングの楽しさの増幅
走行中に感動的な景色を共有したり、休憩ポイントを相談したりと、仲間とリアルタイムで会話できるため、ツーリングの一体感と楽しさが増幅します。
会話の途切れがないことで、休憩時の会話もより弾むようになるでしょう。
製品の選び方
マスツーリングを快適にするインカムを選ぶ際は、「多人数での通信性能」に焦点を当てて検討することが重要です。
同時通話可能人数と通信方式
マスツーリングでは、何人が同時に会話できるかが重要です。
ハイエンドモデルの多くは6人以上の同時通話に対応していますが、製品によって接続方式が異なります。
「メッシュ通信(DMCなど)」と呼ばれる通信方式は、従来のBluetooth接続のように数珠つなぎではなく、グループ内で自由に接続が切れても自動で再接続されるため、大人数での安定した会話に最適です。
通信距離と音質
インカムの性能は、通信距離と音質に大きく左右されます。
製品仕様に記載された最大通信距離は理想値であるため、実際の公道では障害物の影響で短くなることを念頭に置いて選びましょう。
また、走行中の風切り音やエンジンの騒音の中でもクリアな音質を確保するため、ノイズキャンセリング機能が充実しているかどうかも重要なチェックポイントです。
操作性とバッテリー性能
グローブを装着した状態でも直感的に操作できる、物理ボタンの大きさや配置が工夫されているモデルを選ぶと快適です。
充電の手間を減らすため、連続通話時間が長く、短時間で充電が完了する急速充電に対応している製品を選ぶと、ロングツーリングでも安心です。
ブランド間の互換性(ユニバーサルインターコム)
マスツーリングでは、仲間が異なるメーカーのインカムを使っているケースが多々あります。
異なるブランド同士でも接続できるユニバーサルインターコム機能(またはユニバーサルペアリング機能)を持つ製品を選ぶことで、グループ内の接続互換性の問題を解消できます。
使用する際のコツ
インカムの性能を最大限に引き出し、快適なツーリングを楽しむためには、必ず最新のファームウェアにアップデートしておきましょう。
メーカーが提供する最新のプログラムに更新することで、通信の安定性や音質が改善され、予期せぬ接続トラブルを防ぐことができます。
ヘルメットへ取り付ける際は、マイクが口元に正しい位置にくるよう配置し、スピーカーが耳の穴の正面に来るように細かく調整することで、最大限の音質を得られます。
インカムを正しく利用し、仲間と一緒にツーリングを楽しみましょう。